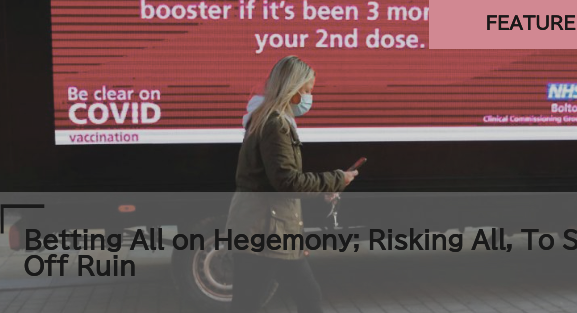Betting All on Hegemony; Risking All, To Stave Off Ruin — Strategic Culture
アラステア・クルック著:13/03/2023
西側諸国は今、すべての戦線で戦うには機能不全に陥り、弱体化している。しかし、西側諸国の権威を失墜させるような屈辱がなければ、撤退はありえない。
時折、「システム」の仕組みの真相を知る窓が開かれる。一瞬、その堕落ぶりが露わになるのである。私たちは目をそらすが、それは啓示である(そうであってはならないのだが)。というのも、このシステムを覆っていた服装がいかにみすぼらしいものであったかが、はっきりとわかるからである。リベラリズムの一見した成功は、そのほとんどがはかない広報活動であるが、その根本的な内部矛盾をより明白にし、より「顔に出る」ようにし、はるかに信用できなくしているに過ぎない。
この解明は、リベラル・モダンに内在する矛盾を満足に解決できないことを物語っている。あるいは、むしろその解体は、ますます全体主義的でイデオロギー的なヘゲモニーへの到達によって、衰えつつある正統性を解決するという選択から派生している。
そのような窓口のひとつが、英国のパンデミック封鎖の不祥事である。封鎖プロジェクトを管理する閣僚のWhatsAppメッセージ10万件が流出し、その紙面が明らかになった。
政府寄りの政治評論家たちの言葉を借りれば、それは何を示しているのだろうか。西側のエスタブリッシュメントが、思春期に互いを非難し合い、民衆をまったく軽んじているという醜い図である。
ジャネット・デイリーが『テレグラフ』紙に書いている。
「ロックダウンは科学の問題ではなく、政治の問題だった。それは、政府が『科学』に従うと言い始めてすぐに明らかになった。このプログラムは、情報を与えるのではなく、怖がらせ、疑いや懐疑を道徳的に無責任であるかのように見せるために作られたもので、科学が行うこととは正反対である」。
「公園のベンチに座ったり、親戚と会ったりすることが犯罪になるような、政府の大規模なプログラムのモデルとなったのは、戦争中の国家であった。恐ろしいレベルの社会的孤立は、国が悪意のある敵に対して集団的な努力で動員されているように見せるために意図的に作られたものだった。東ドイツのシュタージでさえ、子供が祖父母に抱きつくことを禁じたり、異なる世帯に住む者同士の性的関係を違法としたりはしなかったのだ。東ドイツのシュタージでさえ、子供たちが祖父母を抱きしめたり、異なる世帯に住む人々の性的関係を禁止することはなかった。他のあらゆる考慮は、できるだけ多くの人間を殺すことを目的とする侵略軍に対する英雄的な民族闘争に追いやられる必要があったのだ。そして、この敵は目に見えないので、特に陰湿だったのです」。
シェレル・ジェイコブズ
「私たちは、メディアの視線から離れたところで、権力の本性を垣間見ることができたのです。熾烈な誇大妄想と政治家側近からの絶え間ない安心の要求、集団思考と執拗な狙撃の傾向など、その悲惨な逆説が存分に発揮されています。
「1970年代のアメリカ(ウォーターゲート事件)の政治家たちの特徴である「低級な心の質」に対する恐怖に、新たな冷たい連帯感を感じる。しかし、おそらくウォーターゲート事件との最も強い類似点は、...国家の活動が平凡なニヒリズムで満たされているように見えることである。それは、人々を「怖がらせる」ための愉快な十字軍の中にある。それは、隔離されたホテルに閉じ込められた旅行者を嘲笑することである(「愉快な」)。それは、「物語」に対する容赦ない献身にある。
「閉鎖が正しいポピュリストの呼びかけだと本部が判断すると、国家はどれほど熱心に強権的な措置の実施に身を投じたことでしょう。私たちは、ハンコック(厚生大臣)が、公式見解に反した科学者を「変人」「口先だけ」と非難し、「座視」することを謀ったことを知るに至った。我々は、公務員たちが、怪しげな第3次ロックダウンの間、「メッセージの発信を強化する」ためには「恐怖と罪悪感の要素」が「不可欠」だと主張していたという知識を消化しなければならない。また、このロックダウンを前にして、政治家たちが「ピッチを上げる」ための道具として、新たな変種を取り上げたという事実が明らかになったことも残念でならない。おそらく最も腹立たしいのは、パトリック・バランス(科学顧問)が、政府は「科学データに対するメディアの悲惨な解釈を吸い上げ」、「恐怖が高まる雰囲気の中で『オーバーデリバリー』するべきだ」とアドバイスしたことだろう。
フレイザー・ネルソン
「私たちは、首相がひどい仕打ちを受け、説明を受けているのを見ている。ほとんど疑わしいほどだ。ある時、彼はコビッドの致死率についてあまりに無知で、ある数字を100倍も誤解していました。[しかし、最も明らかになったのは、2020年6月、温厚なビジネス・セクレタリーが、ある規則を強制ではなく、勧告的なものにするよう主張したときである。この段階で、コビッドの流通量は激減しており、死亡者数はピーク時から93%減少していた。「なぜ彼女はウイルスのコントロールに反対なのか」と大臣は苦言を呈した。なぜ彼女はウイルス対策に反対するのでしょうか?官房長官はこう反論する(つまり、彼女はリバタリアンなのだ)。
「ロックダウン・ファイルには、閣僚間で送られた何千もの添付ファイルが含まれています。最初に見つけたとき、私は質の高いトップレベルの秘密のブリーフィングが見つかると期待した。その代わり、大臣たちは新聞記事やソーシャルメディア上で見つけたグラフを共有していた。この情報の質はしばしば悪く、時にはひどいものだった」。
ロックダウン・ファイル」は、英国テレグラフ紙が発表したもので、「厄介な」質問をする大臣や公務員は、反対意見を述べられたり、横取りされたり、仲間はずれにされたりする恐れがあることを知っていた毒々しい文化を暴露しています。ロックダウンに反対すると思われる国会議員は、秘密のレッドリストに掲載され、当時の保健長官の補佐官は、「彼らの再選は我々にかかっている。私たちは、彼らが何を望んでいるのか知っているのです」。
しかし、このファイルには、もっと恐ろしいことが書かれている。ファイルの公開に対して、世間はどのような反応を示したのだろうか。平たく言えば それは、大多数の国民が、国家が新しい種類の権威主義に向かう一連の緊急事態を繰り返す中で、非常に麻痺して受動的であり、また足並みを揃えているため、大いに騒ぐこともなく、あまり気づかないということだ。
はっきり言って、ロックダウンのエピソードは、ヘゲモニー、イデオロギー、技術によってもたらされるこの新しい支配のスキーマを象徴するものです。個人の自律性、そして意味を持って生きる人生の探求は、今やその対極にあるものに取って代わられた。服従させ支配しようとする本能、そして無機質で一見脅威的な世界に秩序を押し付けようとする本能です。
監視に基づく自由主義的な管理国家は、アルタ・モエイニが書いたように、「全体主義的で世界を股にかけるリヴァイアサン」へと膨れ上がり、自由民主主義という気持ちの良い外装で不正に偽装された。
パンデミック時に英国で起きた国家権力の行き過ぎは、すべて西洋の政治システムの範囲内で許されたものであることをはっきりさせておく。国家は、より大きな利益のために、いつでも法の支配を停止することができる。パンデミックは、リベラル・デモクラシーの極限状態での働きを露呈したに過ぎず、カール・シュミットの「例外状態」という概念が、民衆に対する国家の「主権」の源泉となるコードであることを伝えています。
この倫理的空白と社会的意味の転覆の中で、西側の政治家たちは、指輪物語風に互いに粗暴な言葉をぶつけ合いながら、その時々の「物語」とメディアの「遊び」が権力マトリックスの中で「自分のレベルを上げる」ことを願うしかない。ぶっちゃけ、より深い指針がない以上、それは純粋に社会病質的なものです。
しかし、リベラルなスキーマの振り子を覇権主義の極端に強く押し出すことで、リベラルなスキーマ全体のスペクトルのもう一方の端に火をつけることになった。個人の自律性と表現の自由を尊重することである。このアンチテーゼは、特に米国で顕著である。
リベラリズムは、フランス革命の初期に、過去の抑圧的な社会階層、宗教、文化的規範からのシステム的解放のプロジェクトとして構想され、解放された個人主義の新しい秩序が誕生することになる。ルソーは、自由主義を、過去からの根本的な脱却、すなわち、家族、教会、文化的規範から個人を切り離し、救済された普遍的統治を構成する一個の要素として、よりよく進化させることだと考えた。
これが初期のリベラリズムの意味であった。しかし、その後のテロルの支配とジャコバン派の大量処刑は、「解放」と社会にコンプライアンスを強制する願望が分裂症的に結びついていることを示すものであった。暴力革命と押しつけられた(ユートピア的な)「人類の救済」という持続的な訴えは、西洋人の精神に対立する2つの極を示し、今日、「ヘゲモニー」への傾斜によって「解決」されようとしています。
個人の急進的な解放と適合的な「世界秩序」の間に内在するこの緊張は、「新しい普遍的価値」によって解決されるはずだった。多様性、ジェンダー、公平性、さらに、以前に受けた差別に対する被害者への賠償金である。この「リキッド・モダニティ」は、(啓蒙主義的な価値観とは異なり)「グローバル・ニュートラル」であり、それゆえ西洋主導の世界秩序を支えることができると考えられていた。
このことに内在する矛盾はあまりにも明白だった。世界の他の国々は、「リベラル」な秩序を、西洋の力を長持ちさせるための、あまりにも明白な装置とみなしている。彼らは、その「宣教師」的な裏面(この側面はユダヤ教・キリスト教圏の外では存在しなかった)や、私たち全員が生きなければならない価値観(啓蒙主義であれ覚醒主義であれ)を西洋が決定すべきとの主張を拒否する。
非西洋は、むしろ弱体化した西洋を観察し、もはや世界的な「支配者」に忠誠を誓う必要を感じない。ペトリン・ロシア、トルコ、エジプト、そしてイランからの)強制的な西側化のメタ・サイクルは終わったのです。
英国(およびヨーロッパ)の閉鎖的なコンプライアンスは、確かに「恐怖のプロジェクト」によって達成されたが、その成功は国民の信頼を犠牲にするものだった。はっきり言って、西洋における権威の権威は、国内でも海外でも、ますます不信感を抱かれるようになっている。
リベラリズムの矛盾と権威の衰退の危機は、ますます深まっている。
カール・シュミットの他の2つのマントラは、第一に、権力を維持するために「使う」か「失う」か、第二に、権力を維持し、大衆を恐れさせ従わせるために、できるだけ偏った「敵」を構成し、「暗い」ものにすることである。
それゆえ、バイデンは代替案を欠き、米国内の敵対者に対する権威を強化するために急進的なマニ教に頼っている(皮肉にも彼らを「民主主義」の敵とみなしている)。また、ウクライナ戦争を道具にして、欧米の対ロシア戦争も光と闇の間の壮大な闘いに仕立て上げている。こうしたマニッシュなイデオロギーの源流は、今のところ、西側リベラリズムを支配している。
しかし、西洋は自らを罠にはめた。「マニッシュ化」は、西洋をイデオロギー的に窮屈な状態に追い込んでしまう。それは、西洋が自ら作り出した危機なのである。単刀直入に言えば、マニ教は、交渉による解決策やオフランプに対するアンチテーゼである。カール・シュミットはこの点について明確であった。最も黒い敵意を呼び起こす意図は、まさに(自由主義的な)交渉を排除することであった。美徳」が「悪」と交渉することなどできるだろうか。
西側諸国は今、すべての戦線で戦うにはあまりにも機能不全に陥り、弱体化している。しかし、(西洋の権威を失墜させるような屈辱がない限り)撤退はありえない。
西側諸国は、自らを救うために、恐怖に支配され、「緊急危機」を管理する「コントロール」システムにすべてを賭けてきたのである。今、その希望は、「用心せよ!」という言葉に託されている。大ボスが怒り狂い、何でもしでかすかもしれない」、これで世界が手を引くことを期待している。
しかし、「残りの世界」は手を引いてはいません。西側エリートの言うことを信じる人は少なくなり、彼らの能力を信頼する人も少なくなった。西側諸国は無謀にも「賭けに出た」のであり、すべてを失うかもしれない。あるいは、もっと危険なことに、怒りにまかせて、他人のゲームテーブルを蹴り倒してしまうかもしれない。